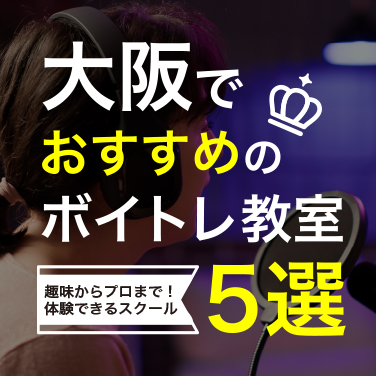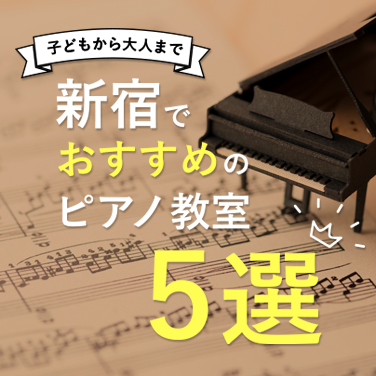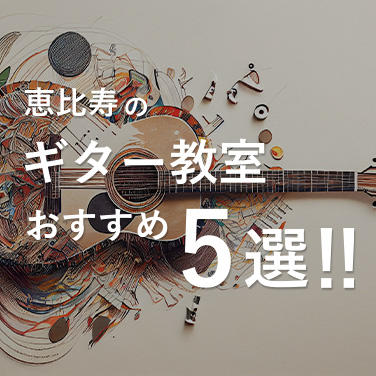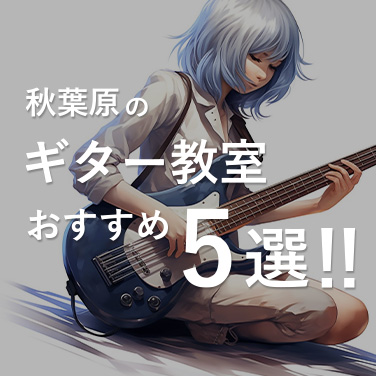【ピアノの歴史と音楽のジャンル】歴史と音楽ジャンルの違いについて学ぼう!
2023.10.30
▷目次
ピアノの歴史や音楽ジャンルの違いを知れば、これまでよりも深みのある音を奏でられる。
「勉強は苦手」「なにそれ?よくわからない」という人へ、わかりやすく解説した記事をお届けします。
歴史と聞くと「難しい」「過去の話」とイメージされますが、ピアノが誕生した背景を学びもっと音楽に近づきましょう。
「知らなければならない」というものではなく、歴史を学ぶことはピアノの成長を振り返ること。
進化の流れを知ることで、親しみも感じられるかもしれません。
【ピアノはいつ生まれたの?】
1709年、ピアノはイタリアのハープシコード製作者に発明されました。
13世紀頃、「クラヴィコード」と呼ばれる楽器が登場しますが、3~5オクターブの音しか奏でられなかったと言われています。
オルガン奏者の練習用に重宝されますが、音量が小さく遠くまで響かない短所を持っていました。
14世紀、ピアノの祖先と称される「ハープシコード」が誕生。音質も豊かで4~5オクターブの音域を出せるようになります。
ところが以前から不満を持っていたハープシコード製作者は、「もっと音の強弱をつけたい」とハンマー仕掛けで弦を打ち鳴らす方法を開発。それが現在のピアノの原型です。
当時は5オクターブ~5オクターブ半まで演奏できたとされており、19世紀初頭に鋼鉄弦や鉄骨フレームが使われてから、7オクターブまで広がりました。
そのためベートーヴェンやショパンはピアノで作曲していますが、バッハはピアノを使っていません。
ちなみにバッハが作曲した「フランス組曲」などは、ハープシコードで作曲されたものです。
そのあと産業革命が起こり、低音2重巻線やソステヌートペダルなどの改良が加えられ、少しずつ一般家庭へも普及します。
ピアノは1本の弦楽器だった
クラヴィコードよりさらに昔の話では、弦を響かせて音を鳴らす「ダルシマー」が有名です。
11世紀頃にヨーロッパで広まったとされ、箱の上に張った弦を小槌で打っていました。
そのため打楽器の要素があったと伝えられ、そもそもの起源も1本の弦を鳴らすところから始まっています。
11世紀とは1001年~1100年。東ローマ帝国や十字軍が存在し、日本で言えば平安時代です。
貴族による琴や琵琶がたしなまれていた時代を考えると、ちょっと強引かもしれませんが、あの時代の楽器も祖先と言えなくもありません。
【日本にはいつ持ち込まれたの?】
ピアノが日本で作られたのは1900年(明治33年)です。社会の流れとしては、パリオリンピックが開催された年。楽器メーカーである「ヤマハ」が最初の1台目を製造し、1928年には河合楽器もピアノを完成させ、そこから上流階級の人へどんどん取り入れられました。一般家庭に普及され始めたのは、戦後の復興を終えてからになります。持ち込まれたのは1823年の江戸時代。貿易が許されていたオランダから鎖国中の日本へ、陸軍医だったシーボルトによって長崎の出島へ持ち込まれます。このピアノは「日本にある最古のピアノ」と言われ、現在は山口県にある熊谷美術館へ展示。保存目的として寄付も募られています。
普及が遅れたのはなぜか
持ち込まれたのは江戸後期だったにも関わらず、本格的な製造は明治中期。それはなぜだと思いますか?シーボルトに持ち込まれたピアノは、1879年から日本海軍の軍楽隊で演奏されるようになりました。軍隊の士気を鼓舞して演奏する。国家行事や儀式の音楽を奏でる。そのために取り入れられた楽器だったので、一般人が使うものではなかったのです。1897年にオルガンが製造され、そのあとのピアノ製造にもつながるのですが、当初は富裕層の子女しか購入できませんでした。それだけ高価なもの。いわゆるお嬢様しか手に入れることができなかった。そして戦後の所得倍増計画によって経済的な負担が減り、頑張って働けばピアノを買えるくらいに発展したのです。1961年、小学校の学習指導要領でオルガンが必修。そこから小学校へオルガンが導入され、一般家庭でもピアノを習い始める人が増えました。習い事の代表と言えばピアノ。そう言われてまだ歴史も浅いですが、最近は「ピアノを弾くことで脳をトレーニングできる」と言われ、子供だけでなく幅広い世代に受け入れられています。
【音楽ジャンルの違い】
音楽ジャンルは、大きく分けて7種類。「ポップス」「ロック」「クラッシック」「ダンス」「ジャズ」「ラテン」「ワールド」です。細かい分類は世界で1,000種類以上あると言われ、まだ聴いたことのない音もたくさん。ピアノで弾くのは、「クラッシック」「ジャズ」「ポップス」。アーティストによってはロックやダンスミュージックで、ピアノ伴奏を取り入れた曲もありますが、それはごく一部です。シンセサイザーで演奏する人のほうが多いので、ピアノではほぼ「クラッシック」「ジャズ」「ポップス」を弾きます。「音楽」という1つのテーマなら分けなくても良いような気もしますが、分類したほうがわかりやすいためジャンルを分けているのです。
では、音楽ジャンルをそれぞれ簡単に説明します。
ポップス
流行している人気曲。「J-POP」や「K-POP(韓国)」と呼ばれ、一般的に広く知られている曲です。そのため厳密な定義はありません。J-POPで言うならSMAPの「世界に1つだけの花」、K-POPなら少女時代の「Gee」などをイメージしてください。他の国の人気曲も、ポップスに含まれます。
ロック
1950年代、アメリカの黒人音楽を起源とします。イメージとしては、ビートルズの曲。日本のアーティストならRCセクションやTMネットワーク、現在はB'zやサンボマスターと言えばわかりやすいでしょう。
クラッシック
クラッシックは西洋の芸術音楽。シューベルトの「アヴェ・マリア」やショパンの「子犬のワルツ」など、数え切れないくらい名曲が存在しています。ピアノ曲だけでなくオーケストラでも演奏され、オペラや声楽曲も含まれるかもしれません。有名なところでは「オペラ座の怪人」や「椿姫」など、舞台で使用される曲もクラッシックに当てはめて良いでしょう。
ダンス
何のダンスを踊るかにもよりますが、ユーロビートやテクノ、ハウスやドラムンベースなど、ディスコブームで流行した音楽を「ダンスミュージック」と呼びます。三代目 J SOUL BROTHERSの「Rising Sun」など、ダンスをメインにしたポップスを含めることも。ただし、他のジャンルをアレンジすることもできるので、線引きする根拠はありません。
ジャズ
アメリカのニューオーリンズで誕生したジャンル。アフリカ系アメリカ人によって広まり、4ビートやスイングするリズムを特徴とし、ブルースやラグタイムを起源とします。日本人のアーティストとしては淡谷のり子が有名ですが、上原ひろみや山中千尋などのジャズピアニストも輩出されています。
ラテン
ラテン音楽は中南米発祥。キューバ系・カリブ系・ブラジル系などの特徴に分けられ、スカ・ロックステディ・レゲエなどが含まれます。2拍子と3拍子の複合で軽快なリズムが特徴。サンバ・ルンバ・マンボに使われる曲も、ラテン系と言って良いかもしれません。あまり馴染もないかもしれませんが、テレビゲームではよく使われています。
ワールド
世界各地域の民族曲や多様な音楽を「ワールドミュージック」と呼びます。例えばフランスの「シャンソン」やイタリアの「カンツォーネ」、ドイツの「ヨーデル」やアメリカの「カントリーミュージック」などです。日本で言えば雅楽や民謡。その地域や国で育まれた音楽と呼べるでしょう。
これらのジャンルは大まかに振り分けているだけで、厳密に言えばもっと細かい違いはあります。ロックやラテンのアレンジは難しいですが、ワールドミュージックはピアノ曲へできるかもしれません。
まとめ
今回はピアノの歴史と音楽ジャンルの違いをまとめました。
・ピアノの誕生は1709年
・日本で製造されたのは1900年
・普及され始めたのは戦後
・音楽ジャンルは7種類(細かく分ければ1,000種類以上)
・ピアノ曲は「クラッシック」「ジャズ」「ポップス」
ピアノは、練習すれば初心者からでもマスターできます。かつては高根の花で手が届かなかった楽器ですが、今は身分や財力に関係なく誰でも演奏できる。習い事へ普及するまで時間もかかっていますが、それはすべて過去の話。好みのジャンルを選び、ピアノ曲へ取り入れましょう。