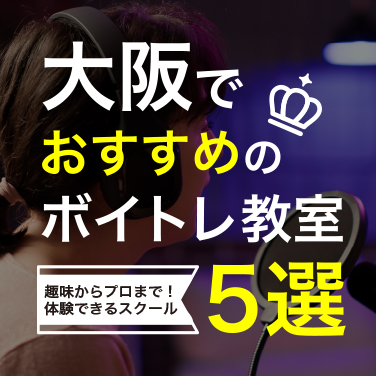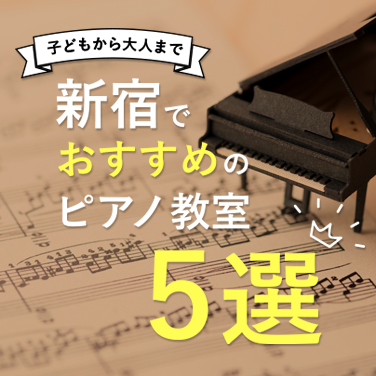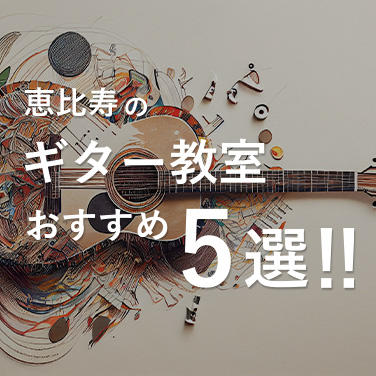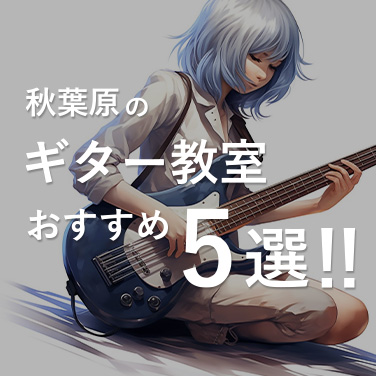【弾き語りの基礎】ピアノ楽曲のためのコード進行と作曲テクニック
2023.11.10
▷目次
ピアノを弾きながら歌う「弾き語り」。難しそうに見えますが、初心者でも可能って知っていますか?幼稚園の先生が園児と一緒に歌う。アーティストがコンサートで披露する。それを目にすると、「特別な人だからできるんだ」「自分には無理」と思われがち。でも、コードさえ覚えれば弾き語りは可能です。いきなり実行できなくても軽い鼻歌あたりから始めれば、ピアノの演奏にも支障をきたしません。さらにコード進行できるようになれば、作曲もできます。「音楽的な才能が必要」とイメージされがちですが、コツさえつかめば普通の人でも曲を作れるのです。そこで今回は、コード進行と作曲テクニックを中心にご案内しましょう。
【コードとは】
コードとは和音。コードには、大きく分けて「メジャーコード」「マイナーコード」2種類あると知ってください。その中でも初心者に覚えて欲しいのは、Cメジャー「ド・ミ・ソ」Gメジャー「ソ・シ・レ」Aマイナー「ラ・ド・ミ」Fメジャー「ファ・ラ・ド」Dメジャー「レ・ファ♯・ラ」この5つを基本コードとします。他にもたくさんありますが、まずは基本コードを弾けるように練習しましょう。楽譜には、コード名のアルファベットを記載しています。例えばCメジャーなら「C」、Gメジャーなら「G」です。コード表記についてはネット上で一覧表を確認するか、もしくは音楽関係の本で調べてください。
コード概要
メジャーコード
根音と根音から長3度の音、根音から完全5度の音
マイナーコード
根音と根音から短3度の音、根音から完全5度の音
*メジャーとマイナーの違い:「長3度の音か短3度の音か」といった1つの音
ご紹介したコードは3和音ですが、4和音で構成される「セブンスコード」と呼ばれるものもあります。セブンスコードは、アルファベットの横に数字が記されたコード。「C7(シーセブン)」であれば、「ド・ミ・ソ・シ♭」。「E7(イーセブン)」であれば、「ミ・ソ#・シ・レ」の音になります。ピアノのコードは、3和音と4和音を合わせると全部で432個!実際に使われるのは36個くらいなので、すべて覚える必要はありません。
【コード進行とは】
覚えたコードを弾きながら、それをつなぎ合わせて進めることです。例えば「アルプス一万尺」であれば、「G→C→D→G→C→G→C→G」という順のコード。もちろんメロディに合わせるため、コードを変えるタイミングは一定ではありません。幼稚園の先生は、これらのコードを進行しながら弾き語りを行っているのです。つまり弾き語りは、コードを覚えて曲を進めれば誰でもできます。ギターの弾き語りを聴いたことがあると思いますが、それと同じイメージだと解釈してください。メロディが複雑であればあるほどコードの種類が多く、それを進行させるリズムも求められます。
それでは作曲のテクニックへ進みましょう。
ピアノで作曲する手順
簡単に言えば「コードを選んで弾く」→「選んだコードにメロディをつける」。これだけです。具体的には「途中でコードを変える」「メロディを伸ばす」「導入部分やサビ部分を作る」「曲の入りや終わりの音を考える」など細かいところはありますが、まずはコードを選ぶところから始めてください。
コードの選び方
メジャーコードは明るい音。マイナーコードは暗い音です。そのためメジャーコードが多い曲は長調。マイナーコードの多い曲は短調になります。自分がどんな雰囲気の曲を作りたいか考えて、必要なコードを選びましょう。「いきなり言われても思いつかない」という場合はコード一覧表を確認しながら、「これはどうかな」と思ったコードを弾いてみてください。「なんとなく好きな感じ」「自分好みの響き」といったコードを確かめられます。それをいくつかつなげれば、コード進行していることになるのです。メジャーコードとマイナーコードを混在させるのもOK!余裕があれば、セブンスコードを含めてもかまいません。
メロディのつけ方
「コードは何となく選べたけどメロディは思いつかない」という人も多く、感覚的に難しい場合は理論的に考えてみましょう。
コードトーンを取り入れる
コードトーンとはコードを構成する音。Cメジャーであれば「ド・ミ・ソ」。この「ド・ミ・ソ」を使って、何でも良いのでメロディを作ってください。コードトーンはコードとリンクしているため、曲を演奏したとき合わない音にはなりません。つまりコード進行の流れが決まっていれば、コードトーンでメロディを作ることができます。例えば「C→A→G」のコード進行であれば、「ド・ミ・ソ→ラ・ド・ミ→ソ・シ・レ」の音を使用。1つの音節にどのコードを含めるか、いくつコードを入れるかにもよりますが、コードトーンでメロディを作るのはコード進行に添う形となり、0ベースで感覚を掘り起こすよりは簡単です。
コードトーン以外の音も含める
「コードトーンだけだと単調になる」「もっとインパクトが欲しい」という場合は、コードトーンとコードトーンの間に別の音を入れる。またはコードトーン自体の間に音を入れても良いでしょう。例えばコード「C→A」の「ド・ミ・ソ→ラ・ド・ミ」を使う場合も、コードに関係ない「ファ」などを途中に入れ、「ド・ミ・ソ→ファ→ラ・ド・ミ」という流れにするのもありです。コードトーンは表記上「Cメジャー=ド・ミ・ソ」と記載していますが、音を使う順番は「ミ・ド・ソ」でも「ド・ソ・ミ」でもまったく問題ありません。コードに含まれる音を使う手法だと覚えてください。ただし、コードトーン以外の音を含める場合は、音のスケールを基準に選びましょう。
【音のスケールとは】
音のスケール(音階)は、曲のキー(主役の音)と相性よく連なる音。キーとはその曲で中心となるコードです。メジャーコードのスケールは、キーから「全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音」と並んでいます。全音とは1つ鍵盤を挟んで隣の音。半音とはすぐ隣の音。例えばCメジャーをキーとするスケールは「ドレミファソラシド」となり、この中からコードトーン以外の音を含めるのは簡単。Eメジャーをキーにした場合、「全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音」を当てはめると、スケールは「ミ・ファ♯・ソ♯・ラ・シ・ド♯・レ♯」となります。スケールはキーに安定感を与える音なので、スケール以外の音を選ぶとちょっと外れた感覚になるかもしれません。
「なんか作曲って面倒」と感じられる場合は、難しく考えず自分の感覚を優先してください。ひとまずコード進行でリズムやテンポを決めて、自分の好きな曲に近いメロディをつけてみましょう。あとは気に入ったメロディの繰り返しや音の強弱などを調整し、演奏時間は短くて良いので1つの音節を作ります。慣れてきたら少しずつ音節を増やし、1つの曲を作りましょう。
「そうは言っても難しい」と思う場合は、作業へ入る前に名曲を聴いてイメージを膨らませてみませんか?ただし、聴いたあと「こんな曲なんか作れない」という気持ちになるなら気分転換の散歩をするか、あるいはコードトーンを使った理論的な手法を選ぶ。「自分もこんな素敵な曲を作りたい」と思うなら、どんどん聴いて感性を目覚めさせてください。曲作りは基本自由です。ここでご説明したのはごく一部なので、いつもどおりピアノを練習してフレーズが浮かぶこともあります。「よし!やろう!」と思って取り組める人。やろうと思っても「コードを覚えるのは苦手」という人。作曲スタイルには個人差があるので、自分のペースで踏み出してくださいね。
【まとめ】
今回はコード進行と作曲テクニックについてまとめました。
・コードを知れば弾き語りもできる
・コード進行を利用すれば作曲も可能
・コードトーンでメロディも考えられる
弾き語りの基本はコード進行。コードさえ覚えてつなげれば1つの曲になり、メロディ部分を歌うだけでカッコよく決められます。コード進行にメロディをつけて曲を作れるので、大きなことを言えば作曲家も夢ではありません。コードを使えば弾き語りや作曲もできますが、覚えられなくてもピアノを楽しめる現実は変わらないのです。そのため「これ以上は頭に入らない」「コードばかり意識してストレスを感じる」などマイナスへ傾くようなら、休憩して心と頭を休ませてください。