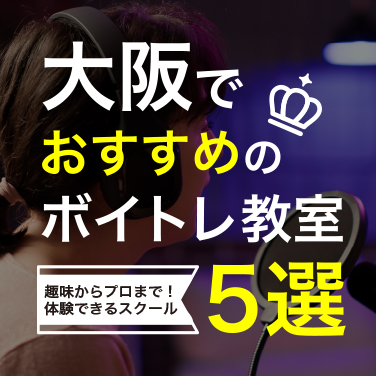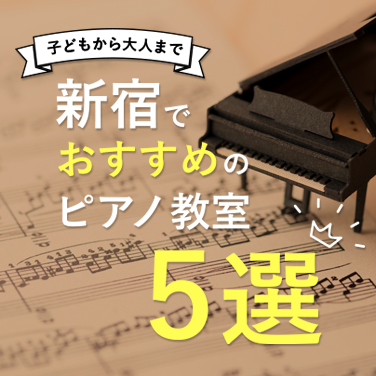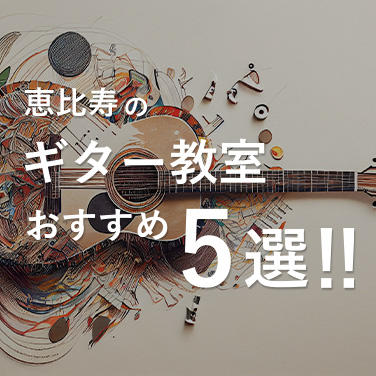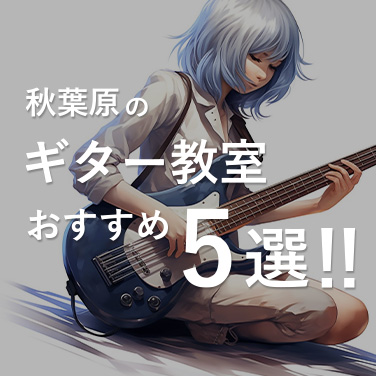【クラシック・ジャズ・ポップス】スタイル別ピアノ練習法
2023.11.16
▷目次
ある程度ピアノが弾けるようになったら、好きな曲を弾いてみたいですよね。ピアノで弾けるジャンルはいろいろありますが、ここではクラッシック・ジャズ・ポップス別の練習法をご紹介します。「ジャンルで練習法が違うの?」と戸惑うかもしれませんが、曲のスタイルが異なるため練習法にも違いがあるのです。「どれがいちばん簡単か」というより、それぞれ求められるスキルが別なので、ジャンル転向でピアノを弾くならそれに応じた練習も必要。どのジャンルへ進むかは人によりますが、自分に合った練習法を見つけてください。
【クラッシック・ジャズ・ポップスの違い】
最も大きな違いは楽譜です。クラッシックはト音記号やヘ音記号を使い、右手と左手で異なる旋律を奏でます。そのため2段構成になっていますが、ジャズとポップスは左手パートをコード表記。つまり右手で弾くメロディはクラッシックと同じ形態ですが、左手のパートは書かれていません。楽譜に書いてあるのは右手メロディ1段だけ。メロディの上にコード表示されているので、右手でメロディを弾きながら、左手でコードを進行させるスタイルです。そうなるとジャズとポップスは演奏スタイルが同じように感じられますが、ジャズは途中でアドリブを入れます。曲全体の7~8割ほどアドリブを入れ、最後は通常のメロディへ戻って終わる。それに比べポップスは、原曲をアレンジしたとしてもほぼ楽曲どおり。楽譜に書かれてないアドリブを入れることはないでしょう。
【演奏スタイルが異なる理由】
クラッシックは16世紀のヨーロッパで生まれました。そのため作曲された音楽は、楽譜に記されすべて残されてきたわけです。ジャズの誕生は19世紀後半。「メロディ→アドリブ→メロディ」という構成になり、「アドリブを自由に入れるならコードのほうが簡単」という考えの元、即興で演奏しやすいコードが使われるようになりました。アドリブはコード進行によって作られるので、最後のメロディにも戻りやすいですが、毎回アドリブがあるのでまったく同じ曲には仕上がりません。ポップスは元々の原曲があり、それをピアノ曲へアレンジしたもの。例えばアニメや映画、ドラマ主題歌など、好きなアーティスの歌を演奏できるので取り組みやすいでしょう。
【クラッシック・ジャズ・ポップスの練習法】
すべてのジャンルに共通することは音感。この音感を鍛える方法の1つとして、お気に入りのピアノ曲を鑑賞してください。これはどの方向へ進んでも同じ。優れた音楽を聴くことで、潜在的な感性を呼び起こせるかもしれません。基礎練習が必要なのはどれも同じ。思いどおりに指を動かせることが、練習をリードしてくれますよ。
【クラッシック】
クラッシックは、楽譜どおりに演奏してください。人によって表現力に違いはあるかもしれませんが、古典的な芸術性を求められます。そのため楽譜を読む力は絶対。まずは音符の種類や記号など、楽譜を読む練習をしましょう。その上で曲の背景を知ることも大切です。例えばベートーヴェンは「ピアノソナタ第8番悲愴」を作曲したとき、耳の異変を感じ始めた時期でした。難聴との関連性は確認されていませんが、少しずつ音が聞こえづらくなった自分、悲しく痛ましい状況を曲へ込めたのかもしれません。こういった背景を知ることでピアノの音色に感情が加わり、豊かな表現力を引き出せるようになります。
【弾けない旋律へ遭遇したとき】
「どの音から練習すれば良いかわからない」という人は、「指をどんなふうに動かすか」といったポイントにしぼって考えてください。音節で区切った練習もありですが、旋律にある弾けない音を取り出しましょう。具体的には「弾けない部分の音と周囲の数音だけ」「1フレーズのみ」という感じで、曲を分解して弾けない指の動きへ集中します。その際に指番号などを確認。合っていれば弾きやすいはずなので、1つ1つ確かめながら弾きましょう。そして弾けない部分を繰り返し、最後に全体をとおした練習をしてください。注意事項は「指が痛くなる」「手が突っ張る」などの異変を感じたらすぐ中止。特に独学で行っている場合は、コンディションの判断が難しいかもしれません。そのため無理せず休憩をとり、再開するかどうかの見極めが肝心です。
【ジャズ】
ジャズはクラッシックと正反対。自由な音楽性を求められるので、楽譜を読めることプラス柔軟性も必要です。3連符の前2つをくっつけ、3つ目にアクセンを加えた「スウィング」と呼ばれる4ビート(4拍)のリズムを基本とし、それに乗ってコード進行させます。他にもリズムはありますが、ほとんど4ビート。感覚を体感するため、メトロノームを使いましょう。2拍と4拍だけメトロノームを鳴らす設定にし、1拍と3拍の感覚も育ててください。このリズムの感覚が、ジャズを弾くためのベースとなります。
【コードの押さえ方】
コードについては、「【弾き語りの基礎】ピアノ楽曲のためのコード進行と作曲テクニック」で説明したとおりなので詳細は省略。例えばDメジャー「ファ・ラ・ド・ミ」であれば、右手でコードを弾き左手で調性(キー)を弾きます。調性(キー)については覚えてください。この弾き方でコード進行をすれば、コードの練習はスムーズに進むでしょう。ただし、「調性(キー)を覚えられない」という場合はコードだけ覚えて、「右手はメロディ左手はコード」という本来のスタイルでかまいません。初心者はまず4ビートのコード進行をできるようになれば、あとはメロディと合わせて弾くだけでOKです。慣れてきたらメロディを崩し、アドリブを入れることができるようになります。
【アドリブの基本】
初心者がアドリブを入れることは難しいので、「これは素晴らしい」と思うメロディを耳コピ。最初は、それに近いようなフレーズを演奏するところからスタートしてください。曲の流れにもよりますが、アドリブはコード進行がスムーズにできるようになったら、真似できるようになるので心配ありません。
【ポップス】
ポップスはジャズより自由度が高く、厳密な定義はありません。「ポップス」=「クラッシック以外のポピュラーミュージック」。そのため練習ポイントも、選んだ曲によって異なります。例えばAdoの「うっせぇわ」はロックなサウンド、Aメロはダークサイドな雰囲気ですが、Bメロ(サビ)へ入ると2拍3連です。コード進行は「A#→Bm」の繰り返し。かなりテンポが速くピアノに慣れていなければ、指がついて行きません。その反対にDREAMS COME TRUEの「未来予想図Ⅱ」はゆったりしたテンポ、「うっせぇわ」と比較してもかなり開きがあります。もちろん初級~上級までレベルに合わせた楽譜があり、それに応じたスキルさえあれば弾けますが、ピアノでポップスを表現するには曲選びが重要になってきます。
【カッコよく弾くためには】
ジャズと同じようにコード進行が大切なのは変わりませんが、ポップスでは雰囲気も気をつけてください。楽譜の読み方など、基本はできている前提でお伝えします。ジャズはビートが重視されますが、ポップスでもリズムはポイント。その上で歌っているアーティストや歌詞の意味などを含め、全体的な雰囲気を膨らませましょう。「右手がメロディで左手はコード」というベースを置き、1つ1つの曲に合わせてリズムやテンポを習得してください。そのためには何度も原曲を聴き、雰囲気をつかんでおくことがおすすめ。
【まとめ】
今回はクラッシック・ジャズ・ポップス別の練習法をまとめました。
・楽譜の違いを認識しておく
・すべてのジャンルで基礎練習は必要
・クラッシックは曲の背景も大事(弾けない箇所は分解して練習)
・ジャズは4ビートとコード進行が重要
・ポップスは基本の上に雰囲気をプラス
ジャンルによって軸となるポイントは違いますが、どこへ進むにしても基本は同じ。指が動かなければ弾けないので基礎練習を続けましょう。ここでご紹介したのはほんの一部なので、本格的に転向したらもっと情報を集めてくださいね。ジャンルを変えることはできるので、弾きたいスタイルを探しましょう。