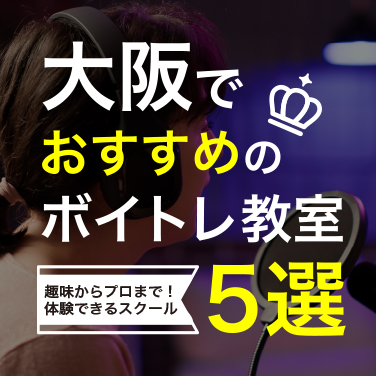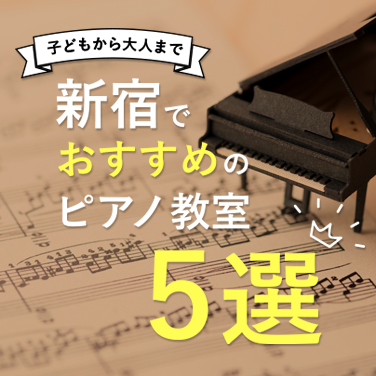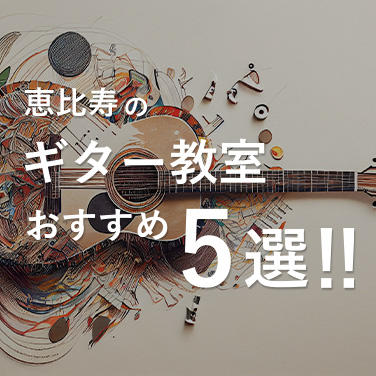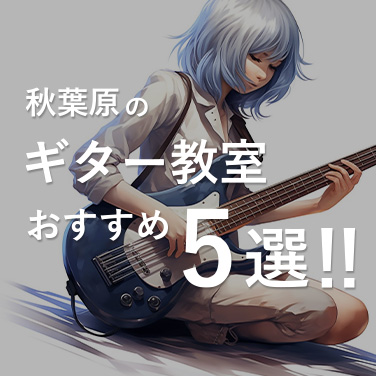【初心者向け】ピアノ基礎テクニック
2023.11.10
▷目次
ピアノ初心者に向けた基礎テクニックをご紹介します。「ひたすたらピアノを弾く」という方法もありますが、どうせ練習するなら自分に合ったやり方を選びましょう。「好きな曲を弾きたい」「でも、何から始めれば良いのかわからない」など、人によっては頭で考えがち。練習の前に諦めてしまい、もしかしたら才能が開花するかもしれない現実を手放しているかもしれません。初心者からでも練習を積めば弾けるようになるので、ピアノに興味を持ったらチャレンジするところからスタートさせましょう。ここでは9つのポイントをまとめたので、思い当たったポイントは参考にしてください。
【練習する環境を整える】
テスト勉強にも共通しますが、集中できる環境を作りましょう。テレビやゲーム、CDやDVD、趣味で集めたコレクションなどが視界へ入れば、気持ちも散漫になります。「ここがお気に入りの部屋だから」「音を気にしなくて済むから」という理由でピアノを置くケースもありますが、初心者であればあるほど環境の影響を受けやすい。つまり「気になる」「意識がそっちへ向いてしまう」という状況が作られ、つい練習を後回しにしてしまうかもしれません。余裕があれば問題ありませんが、ピアノの練習だけに時間を割くのは難しいので、効率良くスキルを上げるためにも集中できる部屋を用意してください。
【正しい姿勢で弾く】
椅子の中央に座り、足裏が床へ着くよう高さを調整しましょう。浅く腰をかけ背筋を伸ばしてください。肩や腕の力を抜いて鍵盤へ指をかけ、肘から手の甲までが床と平行になればOK!姿勢が悪ければ肩こりを起こし、疲れてピアノを弾けなくなります。猫背のままピアノを弾けば必要以上に背中や腰へ力が入り、肩や肘に緊張感も生まれがち。そうなれば指先だけで演奏する形となり、筋肉をうまく動かせず思うような指運びができません。ただし、心がけの問題なので、「集中して練習していたら気づかない」「つい背中が丸くなっていた」という場合もあるため、厳密に意識しなくても大丈夫。ピアノを弾くには正しい姿勢が肝心ですが、人によって違うため自分のしっくりくるスタイルを探してください。
【感情が不安定な日は弾かない】
何らかの出来事が起って落ち着かない日は、ピアノの練習を控えましょう。「自分は関係ないからそんなの気にしない」という人は、このポイントをスルーしてください。ただし、「心がザワザワする」「なんとなく気分が下がった」「イライラが募る」といった場合は、がむしゃらに頑張って練習する必要はありません。喜怒哀楽を曲に反映させるプロなら話は変わりますが、初心者は気持ちの揺れが旋律に影響します。特に怒りや悲しみが大きければ指の動きも乱れ、本来しなやかに弾くべき場面で強く鍵盤を叩いてしまう。どこかに感情をぶつけなければ平常心ではいられない。人によっては安定感を欠いた状態でピアノと向き合うため、「今日はどうしてもうまく弾けない」という状況に陥り、うまく弾けない自分をどんどん追い詰めることになりかねません。「ピアノ禁止」とまでは言いませんが、気持ちが落ち着くまで待ちましょう。
【楽譜を正しく読み取る】
読譜力がUPすれば、楽譜に書かれた単なる「ドレミ」の音階を追うだけでなく、曲に込められたメッセージ性も受け取りやすくなるでしょう。楽譜を読むことは「読譜力」と呼ばれ、全体的な曲の構成を読み取ることにつながります。曲の構成とは1曲の中に含まれるメロディやリズム、音の長さや強弱など、その曲を正しく弾くために組み立てられた設計図。例えばAdagio=アダージョは「遅く/ゆっくり」という意味ですが、「今日は指が動くから」という理由でテンポをあげれば構成から外れます。もちろん自分なりの弾き方も大切したいところですが、ピアノ初心者であればまずは楽譜を正しく読み取ることが優先。楽譜に記された記号を確認して全体を眺め、「この曲はこんな感じ」という感覚をつかんでください。その際は気になる音節を弾き、1つ1つ耳で聴きながら覚えるのもおすすめです。
【最初は片手でも大丈夫!】
これまでピアノに触ったことがなければ、片手(自分の利き手)から練習しましょう。慣れてきたら反対の手→両手という順番でかまいません。両手で練習することに損はありませんが、いきなり始めて難しさを感じれば諦める原因へもつながります。右利きは感性や空間把握。左利きは言語や理論。それぞれまったく異なる得意領域を持ち合わせるため、両手でピアノを弾くには経験が求められます。また「右手は弾けるけど左手は弾けない」というケースもみられ、途中で挫折するきっかけを生むこともあるでしょう。ピアノが弾ければカッコイイことに変わりありませんが、「ピアノを弾く=両手でなければいけない」というルールはないのです。「片手では弾けたことにならない」と思う人もいるかもしれませんが、経験を積み重ねれば両手で弾けるようになるので心配しないでください。
【指トレを行う】
鍵盤への指運びをスムーズにできるようトレーニングしましょう。指の動きが鈍ければ音がつながりません。1つ1つの音に間が生まれるので、何の曲を弾いているか伝わらない状況となります。例えるならパソコンに不慣れな人が、文章を入力する際に人差し指でボタンを押す状態です。最終的にどちらも終わりへ近づけますが、指の動きが遅ければ思うようには進みません。ピアノ初心者へおすすめする指トレは、平らな机に両手を置き1本ずつ上げ下げする方法です。これを10回で1セットとし、1日2~3セット以上は繰り返してください。「なんだ簡単じゃん」と思うかもしれませんが、薬指や小指など、普段あまり使わない指はたかが上げ下げでも思ったより難しい。上げる時間が長くなればなるほど、今までどれだけ使ってなかったか実感できます。ピアノの鍵盤は重いですが、この指トレをすることでストレッチが完了し、意識してしなやかに動かせるようになるでしょう。日常的に続けることで指を早く動かせるようになり、鍵盤を叩く力も強くなります。つき指防止などケガの予防にも有効なので、積極的に取り入れてください。
【音感を鍛える】
好きな曲や有名ピアニストの曲を聴いて音感を鍛えましょう。音感は音に対する感覚。「絶対音感」という言葉もありますが、絶対音感とは音の高さを認識できる能力で、叩いた鍵盤がどの音階に該当するかを判断します。生まれ持って優れた音感を持つ人も存在しますが、トレーニングを重ねれば習得可能。絶対音感まで身に着ける必要はありませんが、ある程度の音の高さがわかればピアノ練習も有利かもしれません。音感は名曲を聴くだけでも鍛えられますが、その際に楽譜で音を確認しながら聴けばより音階もはっきりします。最近は無料でダウンロードできる音感トレーニングアプリも存在するため、ゲーム感覚で遊びながら鍛えるのもおすすめ。手軽に試して音感を養ってください。
【短時間でもOK!】
ピアノ練習は短時間でもかまいません。むしろ練習を始めは、短時間のほうが良い場合もあります。「長く練習すれば上達する」というわけではないので、例え20~30分でも毎日続ければ身に着くでしょう。こう書くと「毎日練習しなければならない」と思い込んでしまいがちですが、「しなければならない」となれば義務感が生まれます。義務感で続けるとピアノ練習を負担に思うかもしれません。そうなると苦痛を伴う時間へ変わるため、「毎日の練習に抵抗がある」「続ける自信がない」という人は、「月曜日~金曜日まで練習する」というようなスケジュールに合わせた予定を組んでください。もしくは「30分練習して10分休憩、そのあと30分練習する」というメニューなど、練習の合間に休憩を挟みましょう。休憩をとらず練習する人もいますが、休憩をとらなければ集中力も途切れます。大人の集中力は平均で50分。長くても90分が限界とされているため、休憩を入れながら短時間の練習を採用してください。
【メトロノームを活用する】
曲のテンポを確かめながら弾けるので、メトロノームを使いましょう。メトロノームは拍感を養うのにベスト!拍感とはリズム感。4分音符と8分音符では拍子が異なります。4分音符は、全音符の4分の1の長さ。8分音符は、全音符の8分の1の長さ。メトロノームを使えば曲に記されたこれらのテンポを保ちピアノを弾けるので、初心者であってもメロディのリズムを崩さなくて済みます。
【まとめ】
今回はピアノ初心者向けのテクニックを解説しました。
・練習環境の整備
・ピアノへ向かう姿勢
・感情の安定性
・読譜力の強化
・片手からの練習
・指トレの実施
・音感の鍛錬
・メトロノームの活用
すべてこのとおり行う必要はないので、自分に合ったポイントを取り入れ練習してみましょう。例え独学だとしても、身に着いた習慣は上達への近道。最初から難易度の高い曲を選ばなければ、練習を重ねて弾けるようになります。そして「初心者からでもここまで弾けるようになった」と自信を持ってくださいね。