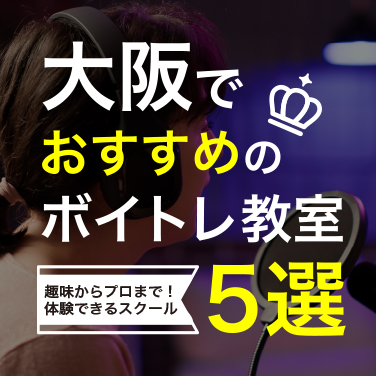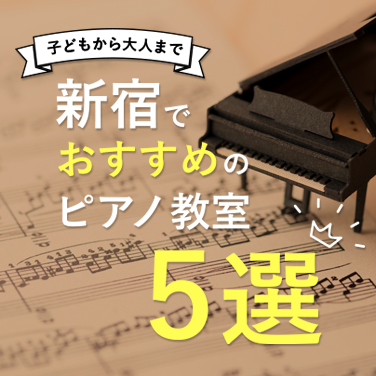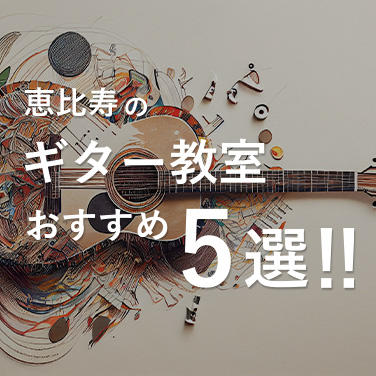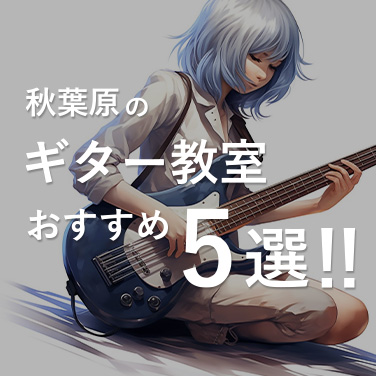【これからピアノを始めたいあなたへ!】初心者が知っておきたい楽譜の読み方と基礎練習方法
2023.11.10
▷目次
ピアノを始めるなら、楽譜の読み方と基礎練習は知っておきたいですよね。楽譜については、「音楽の授業で習ったけど覚えてない」「何を覚えれば良いかわからない」という人も多いのではないでしょうか。小学校や中学校でピアニカやリコーダーを練習しているはずので、確認すれば音符や記号も思い出せるかもしれません。音楽関係の仕事へ就かなければ楽譜とはご縁もありませんが、知識0からでもスタートOK。読み方さえマスターしておけば、ピアノ練習もスムーズに進みます。ここでは楽譜の読み方と基礎練習を解説するので、これからピアノを始めようと思っている場合にお役立てください。
【楽譜を読めたほうが良い理由】
楽譜とは、音符や記号で書き表した曲の構成表。楽譜が読めなければ、ピアノを弾くことはできません。もちろん耳コピで弾ける人も存在しますが、それはほとんど絶対音感の世界。優れた音感があれば楽譜を見ずとも弾けますが、初心者レベルから始めるなら楽譜を読めたほうが有利でしょう。読めなければピアノを弾くとき困りませんか?1つ1つの音符にドレミの音階をつけなければならないし、記号わからなければ「もっと遅く」「もっと強く」「曲の先頭へ戻る」など、意味を書き込まなければなりません。それでも大きな問題はありませんが、「音楽業界を目指したい」「カッコよくピアノを弾きたい」という希望があるなら、読めるほうが演奏もなめらか。楽譜に書き込んだ音階や意味を確認していると、本来の演奏へ遅れをとる可能性もあります。
【楽譜の読み方】
最初からすべて覚えるのは難しいので、弾きながら少しずつ読んでいきましょう。楽譜には音符や休符、強弱や音のつなげ方に関する記号が記載されています。代表的なところで言えば4分音符や8分音符、「とても強く」を意味する「フォルテシモ」や「だんだん弱く」を意味する「デクレッシェンド」などです。他にも強調を意味するアクセントや「なめらかに」を意味する「スラ―」など、たくさんの記号が存在しています。もっと細かく言えば曲の速度や拍子を表わす記号もあり、全部覚えようとすればテンションが下がるかもしれません。
では、どうやって読んでいくか。方法について先ほどお伝えしたとおり、「弾きながら少しずつ」が理想。楽譜は決められたルールに沿って作られるので、基本さえ覚えれば読めるようになります。
音部記号
楽譜の最も左へ位置する記号を確認してください。そこに音の高さを決める音部記号があります。いちばん身近なところで言えば「ト音記号」。これは中心の「ド」より少し右にある「ソ」の位置を示します。ト音記号では、上から4番目の線の上に書かれた音を「ソ」と決めているため、この記号が書かれた楽譜は「ソ」の位置が上から4番目の線の上で、それを基準にして他の音階も決まるわけです。「ソ」が決まったら、楽譜に書かれてある他の音階を確認しましょう。「ファ」の位置を決める「へ音記号」もありますが、初心者であればまずはト音記号から。
音符の長さ
音階がわかったら音符の長さも確認。音符はすべて全音符(4拍)を基準とし、それを何分割するかで長さを区切ります。全音符は符頭だけで穴の空いた丸い状態。2分音符は全音符を2分割した音で、符頭に符幹がつきます。4分音符は全音符を4分割した長さで、2分音符にあった穴が塞がれた状態。8分音符は全音符を8分割した長さで、4分音符に符尾がつけられたもの。「おんぷ」と打ち込んで現れるお馴染みの音符です。16分音符は全音符を16分割した長さで、8分音符に2本目の符尾がつけられたもの。音符の種類は全部で5種類。この長さに音階を合わせれば、ひとまず楽譜を読めるベースができあがったことになります
休符
音の長さがわかったら、音を休めるときの休符にも注目してください。休符も5種類。音符と同じように全休符~16休符まであります。休符の長さは音符と同じなので、「全休符=4拍分休む」「2分休符」=全休符の2分割(2泊分休む)と解釈しましょう。
臨時記号
臨時記号とは音の高さを変化させる記号。全部で5種類ありますが、よく使われるのは「♯=半音上げる」「♭=半音下げる」です。
他にもいろいろありますが、それぞれの記号についてはネット検索や書籍で確認してください。
【楽譜を読めるようになるには】
これまで音楽に馴染みのなかった人は、楽譜を眺める時間を割きましょう。そこで調性や拍子の確認、音符の流れやリズムなどをチェック。わからなければ意味を調べ書き込みます。その上でピアノを弾いて練習してください。「弾けてるかも」と思ったら、今度は書き込みのない楽譜で練習。教本ではなく楽譜単体であれば、1部コピーして書き込み用と通常の楽譜に分けて持つのも良いかもしれません。鉛筆で書き込めば消せますが、消してしまったら意味がわからなくなります。書き込まれていない楽譜で弾けなかった部分は、書き込んだ楽譜で確認するほうが良いので、なるべくならコピーをおすすめ。ピアノを弾きながら何度も確認することで、頭の中へ意味が記憶されるようになります。
基礎練習のすすめ
別記事でも軽く触れていますが、ピアノ初心者に基礎練習は必須!こう書くと強制的に練習させられるイメージも浮かぶかもしれませんが、基礎練習をしておけばそのあとの練習がラクになります。基礎練習に選ぶ曲は、「ツェルニー100番 のハノン」や「ツェルニー40番のショパンエチュード」など、テクニックを問われるような難しい曲ではなく、初級レベルで弾ける曲が良いでしょう。「もっと簡単な曲が良い」という人は、「きらきら星」や「思い出のアルバム」など、比較的ゆったり弾ける童謡を選んでもOK!楽譜を正しく読んで指を動かせるのであれば、曲は何でもかまいません。基本姿勢や鍵盤へ向かう手の位置を意識し、気持ちを盛り上げてください。基礎練習に選んだ曲を弾いて、指の筋肉を柔らかくしておきましょう。
基礎練習におすすめの準備物
少し驚くかもしれませんが、「お手玉」を持ち込んでください。実は「ピアノ練習用お手玉」と呼ばれるものが販売されており、通常のお手玉より大きくピアノを弾く合間に使われています。そのお手玉を使うことで手首の動きがなめらかになり、つかむことで指も鍛えられるでしょう。重さは1個250g。中身はポップコーンに使われる豆です。サイズは15cm×15cm×3cm。ピアノ演奏技術を身に着ける「バスティン・メゾット」で推奨され、ピアノ教室でも取り入れられています。一般的なお手玉より3倍の重さがあるので、慣れるまでは負担かもしれません。遊びの延長でこのお手玉を投げたり握ったりしているうちに、指の力が強化されピアノを弾きやすくなります。キャッチして遊ぶだけでも、リズム感を養えるでしょう。どんな曲でも指に余計な力が入れば、良い音にはなりません。その点、簡単な曲を行う基礎練習のうちにお手玉を扱えば、ちょうど良いバランスの力が身に着きます。
基礎練習を省略して次へ進むのはおすすめできません。なぜなら基礎ができていなければ、ピアノを弾く姿勢や指のフォームも安定せず、中級へ進みうまく指が動かなくなるからです。「速いテンポについて行けなくなる」ということが起こりやすくなるので、「基礎練習って地味だなぁ」と思ってもベースを大切しておきましょう。「基礎練習が続かない」という人は近くを散歩して足を使うか、もしくは目を閉じて好きな音楽を聴くなど、気持ちの切り替えをしてください。
【まとめ】
今回は楽譜の読み方と基礎練習をまとめました。
・弾きながら記号を読む
・最初は楽譜に意味を書き込む
・慣れてきたら書き込みなしで弾く(コピーして2部用意)
・基礎練習は簡単な曲から
・お手玉を使って指の力をつける
「楽譜を読めなければピアノが弾けない」と思われがちですが、弾き始めたら楽譜も読めるようになります。やり始める前はどうしてもハードルが高そうに感じられますが、ピアノ初心者からでも大丈夫なので、1つずつクリアして進みましょう。楽譜が読めれば基礎練習にも身が入ります。次のステップへ進む前に、基礎を身に着けてくださいね。